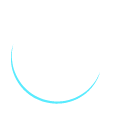ザンビア農村部の保護者たちはもはや傍観者ではありません。学校の指導者に説明責任を求め、予算の執行状況を追跡し、自ら校舎の建設まで手がけるようになっています。一方、ケニアでは、日本の道路補修技術が道路の穴の補修にとどまらず、事業の立ち上げ、子どもたちの登校、失業中だった若者の起業につながっています。
2つの国の抱える課題は大きく異なっていますが、1つの力強い真実があります。それは、コミュニティが主導権を握れば、真の変化が起こるということです。
日本社会開発基金(JSDF)と世界銀行の支援を受けたこれらの取組みは、草の根の活動と賢明な投資を組み合わせると持続的なインパクトを生み出すことを証明しています。
ザンビア:監視役から変革の担い手へ、保護者が教育改革を牽引
ザンビアの辺境地域では、静かながらも力強い変革が始まっています。保護者や地域住民が、子どもたちが登校するだけでなく、学校で確実に成長できるよう取り組んでいます。そのために支出を監視し、欠勤や欠席を減らし、さらには改善のために自分たちの資金を持ち寄っています。
成功を可能にしたのは、「発言力と説明責任:地域の行政サービス向上のためのコミュニティ・エンパワーメント」プロジェクトです。このプロジェクトにより、8万4,000人以上の住民(半数は女性)が、コミュニティ・スコアカードや公共支出追跡などの社会的説明責任ツールのスキルを身につけました。
トレーニングを受けたコミュニティの社会的説明責任委員会が、学校のグラントと予算を追跡し、教科書と机の配布を確認し、教師と生徒の常習的欠勤や欠席を減らし、学校建設プロジェクトの監督まで行っています。
「コミュニティが関与を深めたことで、学校の施設とリソースが改善されました」と、タフェラジコ小学校のウィリアム・バンダ校長は話します。「地域社会の参加によってトイレが3つ作られ、今では300以上の机があります。学校はとても大きな恩恵を受けています」
コミュニティの参画は、以下の通り目に見える成果を上げています。
- 学校の在籍者数が増加:女子を中心に中退者が減少。
- 10代の妊娠が減少:学校の安全性が高まったことで中退者が減少。
- 地域社会がステップアップ:人々が遊び場をつくり貯蓄グループを組織。
生徒と教師の欠勤や欠席の減少、在籍者数の増加、10代の妊娠の減少といった改善は、教師の説明責任の強化、保護者と学校の間のコミュニケーション強化、女児を中心に子どもを学校に通わせることの重要性に対する地域社会の理解の高まりによるものです。
ただし、その恩恵は教育分野にとどまりません。地域社会が主体性をもって取り組んだことが、より広範な市民参加を促進し、有意義な方法で女性のエンパワーメントに貢献しています。例えば、カフンカでは、社会的説明責任委員会の女性たちが、地域社会の取組みに資金を提供し、委員会活動の長期的な持続可能性を強化するため貯蓄グループを設立しています。地域社会は、自らの資金で遊び場や寮を建設するなど、安全性の向上、若年妊娠の減少、定期的な登校に役立っています。